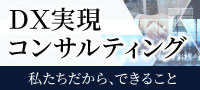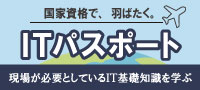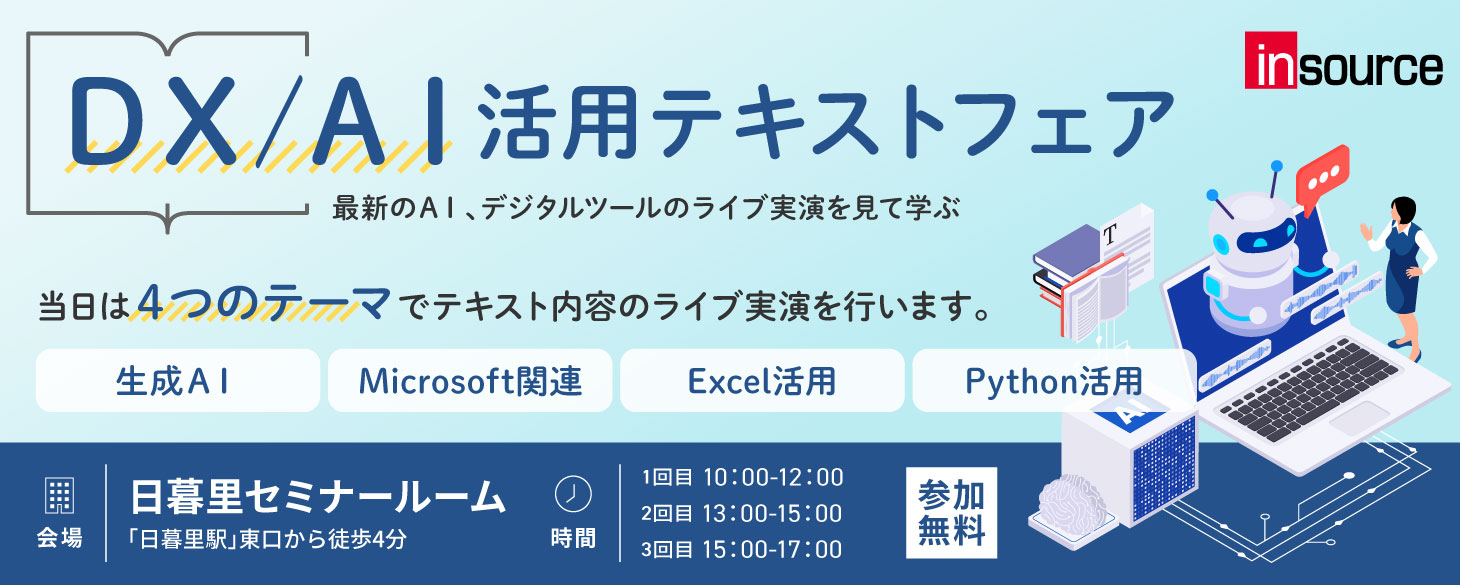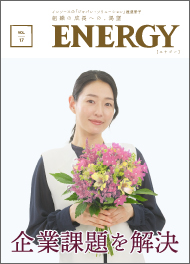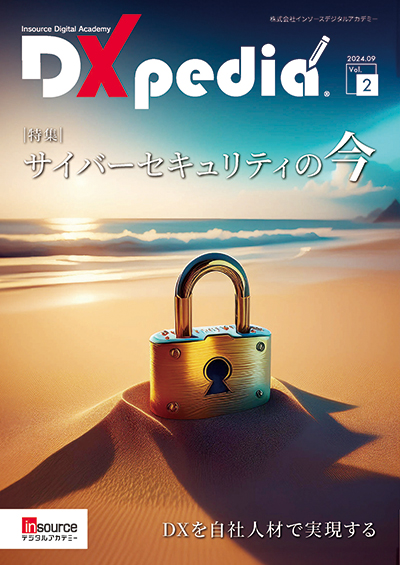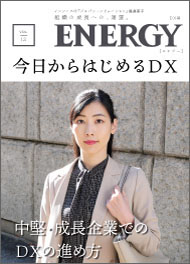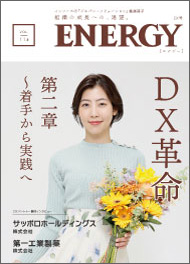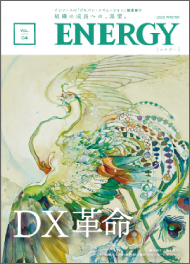2025.07.14
2025.12.18
最近よく聞くOODAループって?
- 文字で構成されています。
※この記事内容は

デキるビジネスパーソンが実践。
不確実な時代に対応する「思考」と「行動」
AI・SNS等テクノロジーの急激な進歩により環境変化が激しく、先を見通すことが困難な現代において、企業や組織が生き残り成長するための「思考様式」「行動原則」としてOODAループが注目されています。
観察し、判断し、決定し、実行するという循環を高速で繰り返すOODAループは、市場変化や競合の動き、そして予期せぬ危機に対しても常に先手を打ち優位性を確立する事につながります。
OODAループの具体的手法を解説
―変化を捉え、先手を取る
OODAループは、アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が提唱した意思決定モデルです。「敵よりも速くOODAループを回す」ことが勝利につながるという洞察から生まれました。
OODAループは以下の4つのフェーズで構成されます。
Observe(観察)
市場トレンド、競合動向、顧客フィードバック、自社データなど、あらゆる客観的データを、外部・内部環境から可能な限り多く収集します。様々な情報ノイズの中から本質的なシグナルを見出す「質の高い観察」が求められます。
Orient(判断・方向付け)
観察で得た客観的情報に対し、自身の経験、知識、文化、成功・失敗体験、遺伝的特性といった主観的要素を重ね、意味付けを行います。単に情報を羅列するのではなく、それらが何を意味し、どのような可能性やリスクを秘めているのかを「腹落ち」させるプロセスとなり、OODAループの中で最も重要なフェーズです。固定観念に囚われずに多角的な視点から物事を捉え、状況を再構築する能力がこの「方向付け」の質を決定します。
Decide(決定)
Orientで導き出された複数の選択肢の中から、最も有効かつ実現可能と思われる行動方針を決定します。「現時点で最善」と判断される行動を迅速に選び取ることが重要です。
Act(実行)
決定した行動をためらうことなく実行に移します。
その結果が再び「Observe」フェーズへとフィードバックされ、新たなOODAループが始まります。この高速なフィードバックループこそ、OODAループの真骨頂です。実行結果を素早く観察し新たな情報として取り込むことで、状況変化に常に対応し、次の一手をより精緻なものへと洗練させていくことができます。

PDCAサイクルとの違いって?―戦略的使い分け
もちろんOODAループは万能ではありません。緻密な計画と体系的な改善が求められる場面では、PDCAサイクルがその真価を発揮します。
Plan(計画)目標を設定し、具体的な達成計画を策定します。
Do(実行)計画を実行します。
Check(評価)実行結果を評価し、計画との差異や問題点を検証します。
Act(改善)評価に基づいて改善策を講じ、次のサイクルへと繋げます。
PDCAサイクルは「大きな変化がない中で、地道に見直しを重ねて良くしていくこと」に適しており、OODAループは「変化が多い中で、すぐに決めて動き、チャンスを見逃さないこと」に強みを発揮します。
両者を、企業の戦略や事業フェーズ、具体的な課題に応じて使い分けたり、複合的に活用したりすることで、より高い相乗効果を生み出すことが可能です。 例えば、日常業務の効率改善にはPDCA、新規事業開発や危機管理にはOODAといったハイブリッドな運用も視野に入れるとよいでしょう。
官公庁におけるOODAループ活用事例をご紹介。
デジタル化と危機管理の最前線
01. デジタル庁における行政サービスの開発
―国民目線での進化
日本の行政サービスはこれまで、ウォーターフォール型開発最初に全部決めてから、順番どおりに進める開発のやり方による大規模システム構築が主流であり、変化への対応が遅れるという課題を抱えていました。しかし、デジタル庁の設立以降この状況は大きく変化し、国民が真に使いやすい行政サービスの実現を目指したアジャイル開発作りながら少しずつ見直して、柔軟に進める開発のやり方を基本原則としています。
Observe(観察)
デジタル庁は、国民からのフィードバック、利用データ、パブリックコメント、海外の先進事例などを継続的に収集・観察します。
Orient(判断・方向付け)
収集したデータを基に、国民がどのような点で困っているのか、サービスのどこに改善の余地があるのかを深く分析し、チーム内で議論を重ね、改善の方向性を定めます。
Decide(決定)
Orientで得られた洞察に基づき、具体的な機能追加や改善、あるいは既存プロセスの見直しといった、次回の短いサイクルでの開発で取り組むべきタスクを決定します。
Act(実行)
決定されたタスクを開発チームが実装し短期間でリリースします。例えば、ある申請フォームでエラーが多発していれば、それを素早く「Observe」し、原因を「Orient」して「Decide」し、次週には修正版を「Act」としてリリースするといった高速な改善サイクルを回します。
これにより、オンライン申請システムの使い勝手向上や、分かりやすい情報提供への改善などの具体的な成果が生まれています。デジタル庁は、OODAループを通じて「GovTech(ガブテック)行政サービスを、もっと早く・分かりやすく・便利にするためのIT活用」を推進し、国民目線でのサービス提供と継続的な改善を追求しています。
出典:デジタル庁情報システム調達改革検討会 最終報告書(案)
出典:2023年度デジタル庁情報システム調達改革検討会のフォローアップ
02. 防衛省におけるサイバーセキュリティ・システム運用
―国家の安全保障を支える迅速性
刻々と進化し、高度化するサイバー脅威に対応するためには、計画性だけでなく、状況に応じた迅速な判断と行動が不可欠です。防衛省は、OODAループの考え方をシステム開発・運用、特にサイバーセキュリティ対策に応用しています。
Observe(観察)
防衛省は、世界各地で発生するサイバー攻撃のパターン、新たなマルウェアの出現、システムの脆弱性情報、国際情勢など、膨大な脅威インテリジェンスをリアルタイムで継続的に収集・分析します。
Orient(判断・方向付け)
収集された情報に基づき、現在のサイバー脅威のレベル、自国のシステムが受けるリスク、そしてそれらに対する優先順位や対応方針を迅速に判断します。
Decide(決定)
導き出された方向性に基づき、具体的な対策(例えば、緊急のセキュリティパッチ適用、特定の通信経路の遮断、監視体制の強化、情報共有のプロトコル変更など)を決定します。
Act(実行)
決定された対策を即座に実行し、その効果を厳密に監視します。同時に、新たな攻撃の兆候がないかを再び「Observe」し、OODAループを高速で回し続けます。
出典:防衛産業サイバーセキュリティ基準の整備について
出典:ロジックモデル(リスク管理枠組み(RMF)関連事業経費)
03. 各地方自治体における危機管理・災害対応システム
―命を守る即応体制
大規模災害が頻発する日本において、地方自治体は住民の命と安全を守るための危機管理・災害対応システムを構築し、運用しています。災害発生という極度の不確実性の中で、OODAループの考え方は真価を発揮します。
Observe(観察)
災害発生時には、被災状況、住民の安否、インフラの損害状況、気象情報、避難所の状況など、多岐にわたる情報をリアルタイムで可能な限り正確に収集します。平時においても、過去の災害データ、ハザードマップの更新情報、住民からの避難訓練のフィードバックなどを継続的に観察します。
Orient(判断・方向付け)
収集した膨大な情報の中から、最も被害が甚大な地域、優先すべき救助・支援活動、必要な物資の種類と量、情報発信の緊急性などを判断し、全体像として状況を把握します。
Decide(決定)
Orientで得られた判断に基づき、救助隊の派遣先、避難所の追加開設、住民への避難指示や情報発信の内容、救援物資の輸送ルートと優先順位などを迅速に決定します。
Act(実行)
決定された行動を直ちに実行に移し、その結果が状況改善に繋がっているかを常に確認し、新たな情報として次の「Observe」に繋げます。
刻々と変化する災害状況をOODAループで捉え、システムの改善や運用に活かすことで、住民の命と安全を守るための迅速な意思決定と行動を支援している具体的な例と言えるでしょう。
出典:新総合防災情報システム(SOBO-WEB)について
終わりに
現代のビジネスリーダーに求められるのは、OODAループ、PDCAサイクルそれぞれフレームワークの特性を深く理解し、状況に応じて使い分けたり、あるいは両者を組み合わせたりする柔軟な戦略的思考です。
これらのフレームワークを組織のDNAに深く刻み込むことで、私たちは不確実な時代を勝ち抜き、持続可能な成長を実現する道を切り拓くことができるはずです。
※本記事は2025年12月18日現在の情報です。
おすすめ公開講座
関連ページ

ITプロジェクトの本質に迫る「極意シリーズ」とは?インソースデジタルアカデミーCTO・小川隆が、豊富な経験と教育への情熱から生まれた研修の背景と、現場で活きる気づき・学びの重要性を語ります。
似たテーマの記事
2025 AUTUMN
Vol.17 企業課題を解決
Vol.17は、「企業課題解決」がテーマです。労働人口の減少など企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、 成長し続けるために経営戦略や人事戦略を改めて考えていくことが求められます。 本誌では、企業インタビューによるDX人財育成の事例や人的資本経営をサポートするソリューション事例をご紹介しております。
Index
2024 WINTER
DXpedia® 冊子版 Vol.3
Vol.3は「普及期に入ったAI」がテーマです。AI活用を見据え管理職2,200人を対象とする大規模なDX研修をスタートさせた三菱UFJ銀行へのインタビューや、AIの歴史と現在地に光を当てる記事、さらに因果推論や宇宙ビジネスといった当社の新しい研修ジャンルもご紹介しています。
Index
-
冊子限定
【巻頭対談】管理職2,200人のDX研修で金融人材をアップデートする
-
冊子限定
ChatGPTが占う2025年大予測
-
冊子限定
AI研究がノーベル賞ダブル受賞
-
冊子限定
チョコとノーベル賞の謎
-
冊子限定
宇宙ビジネスの将来
-
冊子限定
【コラム】白山から宇宙へ~衛星の電波を自宅でとらえた
2024 AUTUMN
DXpedia® 冊子版 Vol.2
『DXpedia®』 Vol.2は「サイバーセキュリティの今」を特集しています。我が国トップ水準のリスク関連コンサルティング会社であるMS&ADインターリスク総研の取締役に組織の心構えをうかがいました。このほかサイバー攻撃やセキュリティの歴史を当社エグゼクティブアドバイザーがひもといています。
Index
-
PICKUP
【巻頭対談】サイバー攻撃への備え 従業員教育が欠かせない
-
冊子限定
「復旧まで1カ月以上」が2割〜国内のランサムウェア被害調査
-
PICKUP
サイバーセキュリティ今昔物語
-
冊子限定
DXpediaⓇ人気記事
-
冊子限定
【コラム】白山から宇宙へ~アポロが生んだ技術の大変革
2024 SUMMER
DXpedia® 冊子版 Vol.1
IDAの新しい冊子『DXpedia®』が誕生しました。創刊号の特集は「ChatGPT時代」。生成系AIを人間の優秀な部下として活用するための指示文(プロンプト)の例を始め、Web版のDXpediaで人気を集めた記事を紹介、さらに宇宙に関するコラムなどを掲載しています。
Index
-
冊子限定
プロンプトでAIをあやつる~前提や体裁を正しく指示して完成度UP!
-
冊子限定
AIそれはデキる部下~インソースグループの生成系AI研修
-
冊子限定
AIと作る表紙デザイン~生成系AIを有能なアシスタントにしよう
-
冊子限定
【コラム】白山から宇宙へ~未来を切り拓くSX(
-
冊子限定
DXpediaⓇ人気記事
2023 AUTUMN
Vol.12 今日からはじめるDX
Vol.12は「中堅・成長企業でのDXの進め方」がテーマです。他社リソースを上手に活用するために身につけたい「要求定義と要件定義」を解説しました。 2人の「プロの目」によるDXの取組みへのヒントに加え、身近なアプリではじめるDXを活用事例とともに紹介します。DXお悩みQ&Aでは、中小・成長企業特有の事例を取り上げました。DXをはじめるなら「今」です。
Index
2023 SPRING
Vol.11 DX革命 第二章~着手から実践へ
vol.4の続刊であるVol.11は「DX革命の実践」がテーマです。 本誌の前半ではDXの課題を4段階に整理し、各段階の解決策である研修プランを掲載しています。 後半では弊社が研修を通じてDXを支援した、各企業様の事例と成果を紹介しています。自社のDX実践に際して、何がしかの気づきを得られる内容となっています。
Index
2020 WINTER
Vol.04 DX革命
Vol.04はDX推進のための効果的な手法がテーマです。DXは喫緊の経営課題である一方、IT人材不足や高いシステム導入コストにより実現が難しいと捉えられがちです。そこで本誌では、今いる人材で低コストに推進するDXについてご紹介しております。
Index
お問合せ
まずはお電話かメールにてお気軽にご相談ください
お電話でのお問合せ
03-5577-3203